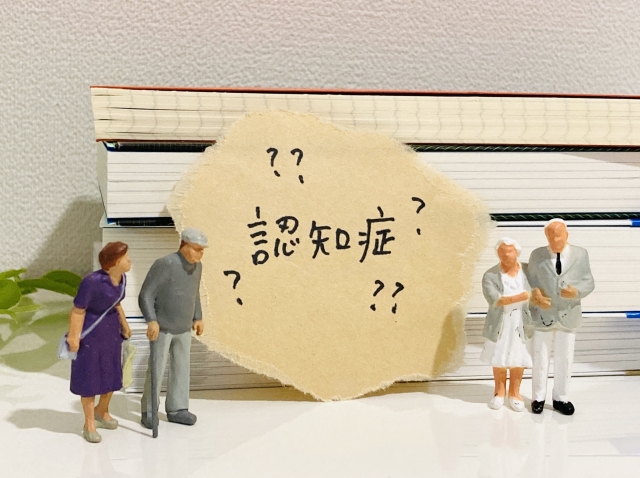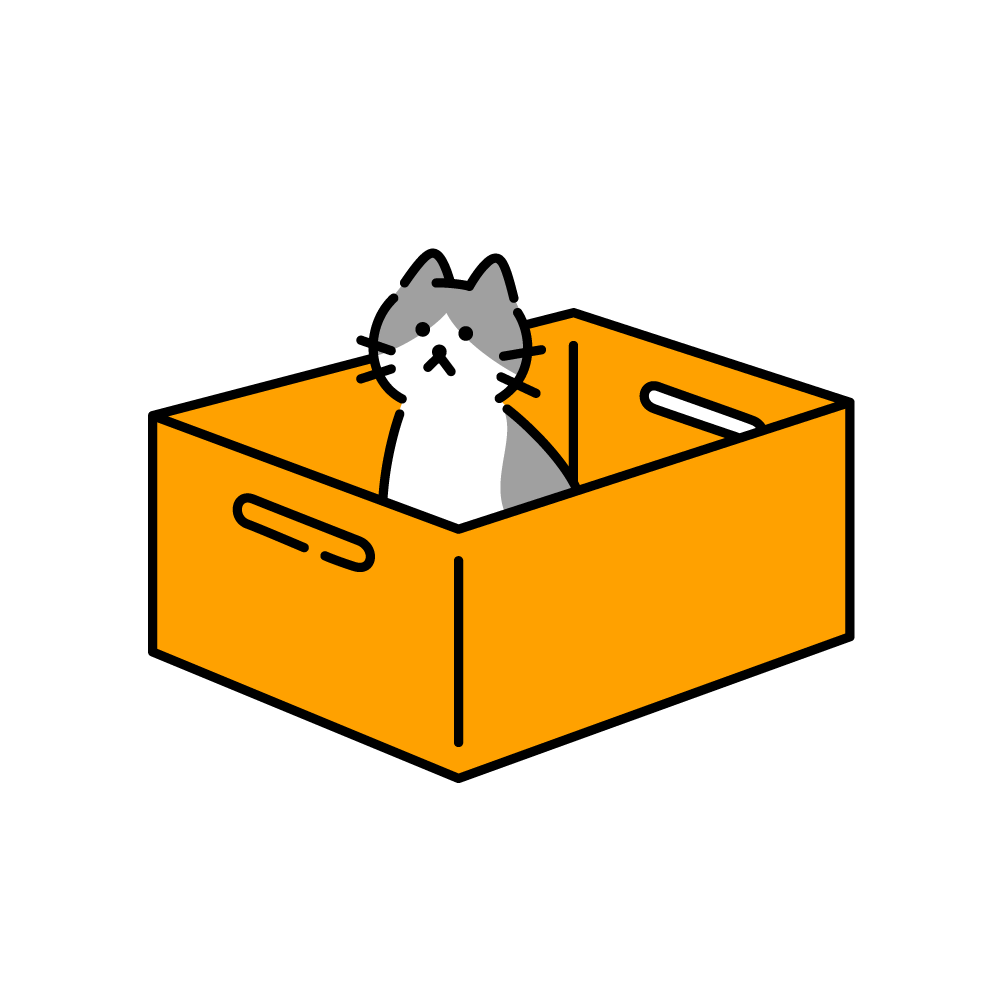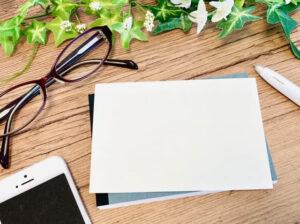ヘルパーA男
ヘルパーA男認知症ごとの特徴がわかりづらい・・・



具体的にはどんな症状があるの?
介護職として働くうえで接する機会が多い認知症のご利用者さま。2025年には高齢者の5人に1人が罹患すると予測されています。
代表的な認知症はアルツハイマー型認知症・脳血管性認知症などですが、認知症による症状は多岐にわたります。
今回は認知症の種類と特徴を中心に解説します。認知症の種類や原因を知り、あらゆる認知症に対応できるように学びましょう。
認知症とは?
認知症は病名ではありません。さまざまな原因によって脳の働きが悪くなり、自分自身や周囲の状況などがわからなくなる状態を認知症といいます。
認知症を発症すると、以前と同じような日常生活や社会活動を送ることが困難になるケースがあります。
認知症には脳へのダメージによって引き起される中核症状と、中核症状にその人の置かれてる環境や本来の性格が影響して現れるBPSD(周辺症状)があります。
2つの症状を具体的に解説していきます。
中核症状
中核症状は、認知症になるとほとんどの方に出る症状です。
具体的には、以下のような症状があります。
- 記憶障害:食事を食べたことを忘れてしまう
- 見当識障害:今日の日付がわからない
- 実行機能障害:献立を立てて料理を作れなくなった
- 理解・判断力の障害:架電の操作ができなくなった
中核症状は、見当識障害などによる認知機能の低下により、周囲の状況を正しく認識できなくなります。
その結果、日常生活上にも支障が出始めてさらに症状が進行すると、介護が必要な状態になります。
BPSD(周辺症状)
BPSD(周辺症状)は、記憶障害などの中核症状やその人の性格、置かれている環境などが影響して出る症状です。
具体的には、以下のような症状があります。
- 人格変化:穏やかだった人が怒りっぽくなる
- 徘徊:周辺をうろうろして落ち着かない
- 妄想:物を取られたと事実ではないことを思い込む
BPSDは、不適切なケアでも発症します。
たとえば施設に入所したばかりの認知症の方が、自分がいる場所を認識できていないとします。「自分がどこにいるかわからない」「周りに知らない人がたくさんいる」といった状況では、誰でも不安になるでしょう。
そのような状態で「ケアを強要する」などの不適切なケアをすると、ケアの拒否や暴言、暴力などにつながる恐れがあります。
BPSDの症状がある場合は「不適切なケアをしていないか」を一度振り返ってみるのも大切です。
認知症患者数の現在とこれから
2022年10月現在、国民年金の納付期間が5年間延長になるかもしれないとニュース番組で取り上げられています。
これまで国民年金の納付期間は20歳~60歳までの40年間でした。しかし少子高齢化によって現役世代が減少している現状を踏まえ、国民年金の納付期間を20歳~65歳の45年間へ延長する案が出ています。
加齢によって認知症は発症しやすくなります。高齢者の増加にともなって、認知症患者数も増加すると予測されています。
日本の総人口と高齢者の割合
総務省統計局の統計からみた我が国の高齢者の発表によると、2022年以降の総人口と高齢者数は以下の通りです。
| 総人口数 | 高齢者数 | |
| 2022年 | 12471万人 | 3627万人 |
| 2025年 | 12254万人 | 3677万人 |
| 2030年 | 11913万人 | 3716万人 |
| 2040年 | 11092万人 | 3921万人 |
2022年現在、日本の人口の約3割が高齢者です。そして、今後も増え続けると予測されています。
今後の認知症患者数
平成29年度高齢者白書によると、認知症患者数の推移は以下のとおりです。


出典:平成29年高齢社会白書外部サイト第1章第2節3高齢者の健康・福祉より
認知症患者は2012年には7人に1人の割合でしたが、2025年には5人に1人が認知症になると予測されています。
これらのデータからも、認知症について理解を深める必要性を感じられます。
認知症の種類
今後も増加することが予測される認知症ですが、その種類は次のようなものがあります。
- アルツハイマー型認知症
- 脳血管性認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
- アルコール性認知症
- 大脳皮質基底核変性症
それぞれ解説します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、患者数がもっとも多い認知症です。
厚生労働省の認知症施策の総合的な推進についてによると、全体の認知症患者数の中で67.6%がアルツハイマー型認知症の方です。
具体的には、次のような症状があります。
- 話していた内容を忘れてしまうことが何度もある
- 食事を食べたことを忘れてしまう
- 今までの趣味をやらなくなった
- 自分の部屋がわからない
アルツハイマー型認知症では、アミノイドβなどの不要なタンパク質が脳の海馬を含む側頭葉内側に溜まります。タンパク質が溜まると脳の神経細胞が減少し、脳の海馬を含む側頭葉内側が萎縮します。
アルツハイマー型認知症は記憶障害が特徴的です。海馬は新しい記憶を整理する役割があるため、萎縮してしまうと新しい出来事を忘れてしまいます。
脳血管性認知症
認知症の中で2番目に患者数が多いのが、脳血管性認知症です。
具体的には、次のような症状があります。
- できること・できないことの差が激しい
- 感情のコントロールが難しい
- 体調によって症状が変わる
脳血管性認知症は「脳の血管が詰まる(脳梗塞)」「脳の血管が破れる(脳出血)」といった原因で発症します。
脳に十分な血液や酸素が運ばれないことで脳細胞が減少します。ダメージを受けた部位や度合いによって現れる症状が異なります。
ダメージを受けていない部位の脳の機能は正常に保たれているため、それぞれの症状や状況に合わせた対応が必要です。
レビー小体型認知症
認知症の中で3番目に患者数が多いのが、レビー小体型認知症です。
具体的には、次のような症状があります。
- 実在しない人や虫などが見える
- 多量に汗が出る
- 手足が震えるなどのパーキンソン症状がある
- 寝ているときに寝ぼけて大声を出す
レビー小体型認知症は、レビー小体というタンパク質が脳の海馬を含む側頭葉内側に溜まります。レビー小体が溜まると神経細胞が減少し、脳の海馬を含む側頭葉内側が萎縮します。しかし、アルツハイマー型認知症と比べると萎縮度合いは軽度な傾向です。
特徴の1つであるパーキンソン症状は、レビー小体が原因で発症します。脳の中の黒質という部分にレビー小体が溜まると神経細胞が減少します。すると、黒質で作られるドパミンという物質の量が減り、パーキンソン症状が出現するのです。
前頭側頭型認知症
前頭側頭葉型認知症は、難病に指定されています。
具体的には次のような症状があります。
- 他人の目を気にせず自分勝手に行動する
- 毎日同じ時間に同じ行為をする
- 怒りやすくなる
- 自分で考えて行動しなくなる
前頭側頭葉型認知症は、タウ蛋白やTDP-43などのタンパク質が脳の前頭葉や側頭葉に溜まります。
タウ蛋白などが溜まると神経細胞が減少し、前頭葉や側頭葉が萎縮します。前頭葉は「自分を客観的に捉えて人を人らしく律する役割」があるため、萎縮により反社会的な行動をしてしまうケースも少なくありません。
「悪意無く万引きをしてしまう」など、他人の目を気にしないような行動も特徴の1つです。
アルコール性認知症
アルコールによって引き起こされる認知症をまとめた名称が、アルコール性認知症です。
具体的には次のような症状があります。
- 歩行が不安定になる
- 手が震える
- 日時や自分が居る場所がわからない
- 感情や行動のコントロールができない
アルコール性認知症は、アルコールの過剰摂取により脳の栄養が不足することが原因で発症します。
アルコールの分解にはビタミンB1が必要であり、アルコールにビタミンB1が消費されることにより脳に送られるビタミンB1が減少してしまいます。脳に必要なビタミンB1が不足すると、前頭葉を中心とした脳が萎縮してしまいます。
前頭葉の萎縮により、感情や行動の制限ができないケースもあります。また、アルコールの摂取で血栓ができやすくなるため、脳梗塞などの脳血管障害を併発する恐れもあります。
大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核症候群は難病に指定されています。
具体的には、次のような症状があります。
- 手足が震えるなどのパーキンソン症状がある
- 言葉を理解するのに時間がかかる
- 毎日同じ時間に同じ行為をする
- 身体の左右どちらかが動かしづらい
大脳皮質基底核変性症は、大脳皮質(前頭葉や頭頂葉)と皮質下神経核の黒質と淡蒼球を中心とした神経細胞が減少し、脳が萎縮します。
残った神経細胞とグリア細胞内に異常リン酸化タウが溜まっている状態が確認されていますが、なぜ神経細胞が減少するのかは不明です。
また、左右非対称に大脳皮質が萎縮する特徴があります。「身体の左右どちらかが動かしづらい」といった身体的な症状に繋がります。
認知症は脳がダメージを受けた部位によって症状が違う
今回ご紹介した認知症以外にも、数多くの種類があります。血管障害やタンパク質が溜まることによって、脳はダメージを受けます。そのダメージを受けた部位によって、現れる症状は異なります。
認知症の症状が発症する理由を知り、実際のケアに役立ててみましょう。